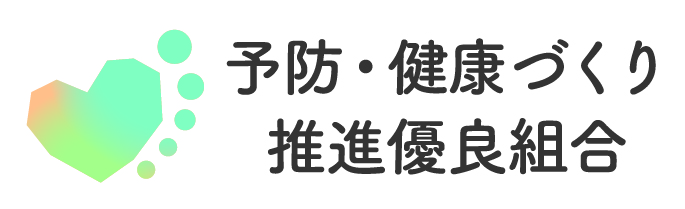2025年01月09日
(転載)日本予防医学協会
健康づくりWEBかわら版 2025年1月号より
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
ニューノーマル時代の口腔ケアとは?
~“New Normal” for Oral Care~
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
1歳半から2歳半の乳幼児期は「感染の窓」が開くといわれ、
むし歯菌に感染し定着を防ぐために、子どもと大人は食器の共
有をしないことが推奨され広く伝わっていました。
歯科では定説でありましたので、歯科保健指導にてその説を伝
え、そして、それをまじめに実践していた方は多いのではない
でしょうか。
しかし、その定説が翻ったのをみなさんご存知でしょうか?
2023年9月、日本口腔衛生学会は以下の見解を示しました。
「食器の共有をしないことで、う蝕予防できるということの科
学的根拠は必ずしも強いものではない」「親の唾液に接触する
ことが子どものアレルギーを予防する可能性を示す研究が報告
された」ことから、食器を共有する生後5ケ月以前に親の唾液
には、すでに暴露しているので気にしすぎなくてよいとのこと
でした。[1]
----------------------------------------------------------
むし歯と歯周病菌はどこからやってくる?
----------------------------------------------------------
① むし歯菌 母親(親)⇒ 子
生まれたばかりの赤ちゃんのお口の中には、むし歯菌や歯周病
菌は存在しません。しかし、次第に主に母親由来の口腔細菌が
定着していることがわかっています。家族間で菌を共有し乳幼
児期の口腔にむし歯菌も常在菌として定着していきます。[2]
② 歯周病菌 パートナー? 親?⇒ 子
数ある歯周病菌の中でも3つの歯周病菌の複合体をレッドコン
プレックスと呼び、重度の歯周病に関与しているようです。
この中でも最強最悪の菌が“Pg菌”です。Pg菌は18歳以降に感
染することから「パートナーからの感染」といわれています。
③ 歯周病菌 犬や猫 ⇔ 飼い主
犬と飼い主も相互に菌を共有しているという報告があります。
犬の顔の形状や小型犬の小さな顔の場合は、歯根と目や脳まで
の距離が近く顎の骨も小さいことから、顔が腫れたり、目から
膿が出たりと、犬の歯周病は思いもよらぬ重篤な事態になるこ
とがあるので注意が必要です。
因みに犬の歯石除去は全身麻酔になります。
----------------------------------------------------------
感染したらOUT? マイクロバイアルシフト
----------------------------------------------------------
唾液を介して菌は伝播・共有していきますが、口腔常在菌の
バランスがとれていれば、むし歯や歯周病は発症しません。
お口を取り巻く環境のバランスが崩れて、ある種の口腔細菌が
病原性を高めることを"マイクロバイアルシフト"といいます。
高病原性にシフトした状態のバイオフィルム[注1]が、むし
歯や歯周病を発症させ進行していきます。
特に、歯周病菌は血液の鉄とタンパクが大好物です。歯磨きの
時に出血する方は、歯周ポケットの内側にできた潰瘍から出血
しています。歯肉出血は栄養が増え、歯周病菌が一気に増殖し
"マイクロバイアルシフト"がおきます。
喫煙も歯周病菌が優位になる要因になります。
[注1]
お口の中のバイオフィルムは歯垢(プラーク)のことです。
複数の細菌がコミュニティをつくり、身を守るために増殖し
粘着性の膜を形成していきます。排水溝や川底の石のヌルヌ
ルとしたものがバイオフィルムです。
----------------------------------------------------------
感染からの脱出! 防御の方法
----------------------------------------------------------
むし歯や歯周病にならないためには、厄介者のバイオフィルム
の量を減らしたり除去する必要があります。粘着性なので、う
がいや強い水流を当てるくらいでは簡単には落とせません。
しっかりと歯ブラシ等の毛先で物理的に擦って膜をはがす必要
があります。
●セルフケア
歯ブラシによる歯磨きだけではきれいに磨いたと思っていても
実は6割程度しか落とせていません。
歯間部は、デンタルフロスか歯間ブラシなどの歯間清掃用具を
使って磨き残しがないようにしましょう。
歯磨剤は、高濃度フッ素[注2]をぜひ使ってください。
歯を修復し耐酸性の強い歯にし、静菌作用があります。予防歯
科の効果で最も高いエビデンスがあるのはフッ素の利用です。
●プロフェッショナルケア
セルフケアで落としきれないバイオフィルムは、歯科医院にて
専門的な機械を使い歯周ポケット内までクリーニングする定期
的なメインテナンスを受けましょう。
[注2]
6歳以上は、フッ素濃度1500ppmの歯磨剤の使用を推奨
6歳未満は、500ppmから1000ppmの歯磨剤の使用を推奨 [3]
----------------------------------------------------------
★ 最後に・・・ ★
----------------------------------------------------------
お口の菌の共有はゼロにはできませんが、気にかけすぎる必要
もありません。
但し家族等からの菌の伝播は明らかです。口の中を当たり前に
清潔に保つことは、自分のみならず家族や周囲の方々への配慮
となるのではないでしょうか。
新年の良いスタートを爽やかなお口でお迎えいただき、ご家族
みなさまの口福を祈念いたします。
今回の記事は次の資料を参考・引用して作成しました。
[1] 日本口腔衛生学会 乳幼児期における親と食器共有について
https://www.kokuhoken.or.jp/jsdh/statement/file/statement_20230901.pdf
[2] PRESS RELEASE(2022/01/25)
九州大学 口腔予防医学分野 教授 山下喜久
母子間の口腔細菌共有を高精度に検証
[3] 日本小児歯科学会「フッ化物配合歯磨剤の推奨される利用方法について」
https://www.jspd.or.jp/recommendation/article20/
・麻布大学 島津徳人
動物の歯周病は人間からうつる?? - 麻布出る杭プログラム
https://www.azabuderukui.info/project/periodontal-disease-in-animals/
・“歯周病”からヒトと動物の共生を考える ー418(良い歯)プロジェクト 2024ー
https://www.azabuderukui.info/wp-content/uploads/2023/05/pj2024_12.pdf
・大阪大学 口腔分子免疫制御学講座予防歯科学 教授 天野敦雄
昭和学士会誌 第79号 第5号(600-608頁,2019)
DrとDH,一緒に学ぼう:歯周病とう蝕の最新バイオロジー
以上